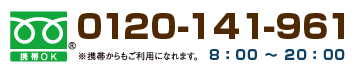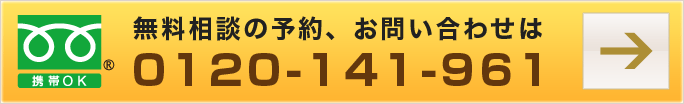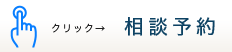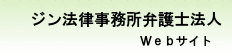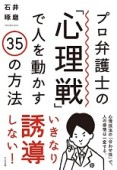保釈
保釈
保釈について
保釈という制度があります。
刑事事件で、捕まっているときに、裁判の結果を待たずにお金を積んで釈放してもらう制度です。
これは、逮捕されて、すぐに使える制度ではありません。
裁判になった後、初めて使える制度です。

流れで説明しますと、逮捕されると、多くの事件ではその後に10日間の勾留がつきます。
これは+10日間延長されることがあります。
その期間に、検察官が、裁判にかけるか、かけないか決めます。
かけない場合には釈放。
かける場合には、そこから初めて保釈という制度が使えます。
通常は、捕まったまま裁判にかけられると、裁判が終わるまで釈放されません。
保釈という制度を使って、お金を納めると、それを担保に一旦釈放されることになります。
保釈金は事件や状況によっても違いますが、昔よりも高くなっていると言われています。
150~200万くらいのケースが多いと思います。
テレビで報道されるような経済的な犯罪だと高額になることが多いですね。
これは担保ですので、裁判が終われば戻ってきます。
ただ、お金を積めば必ず認められるというわけでもなく、争っている事件だったり、関係者と供述が違ったりすると、証拠を隠滅する危険があるとして、裁判がある程度進まないと保釈が認められないケースもありますのでご注意下さい。また、覚せい剤取締法違反事件や暴力団関係の事件では保釈が認められにくい傾向にあります。
保釈請求時には、身元引受人の身元引受書、場合によっては被告人の生活状況を記載した陳述書、被告人の給与明細等を資料として提出します。
起訴後、ただちに保釈請求をしたい場合には、起訴される前から準備しておくことが望ましいです。
保釈請求のご依頼、刑事弁護人をお探しの方は、お早めにご連絡ください。







保釈と実刑判決
第1審で保釈が認められた後、判決の内容が懲役や禁錮を内容とする実刑判決(執行猶予が付かない判決)であった場合、保釈の効力は失われます。
判決言渡し日に収監されることになります。
再度の保釈が認められれば釈放されることになりますが、一度実刑判決が出ていることなどから、保釈の判断は厳しくなります。裁判官の裁量で保釈が認められるかどうか、にかかってしまいます。
また、保釈が認められる場合も、通常は保釈金は第1審よりも高くなります。5割増し程度のことが多いでしょう。
刑事訴訟法343条で、「禁錮以上の刑に処する判決の宣告があつたときは、保釈又は勾留の執行停止は、その効力を失う。」とされています。
判決言渡し前から、実刑判決だった場合を想定して、再保釈申請の準備、また控訴をするかどうかなども考えておく必要があります。
保釈と控訴審での実刑判決
実刑判決と保釈の失効については、上記のとおりなのですが、これは第1審の場合です。
控訴審での判決の場合、若干、状況が変わってきます。
控訴審でも再保釈が認められた後、控訴審判決で実刑判決となった場合も、保釈の効力が失われると考えられています。
ただし、多くの高等裁判所では、判決言渡日に被告人を収監することはしていない運用がとられています。東京高等裁判所などでは、判決から1週間程度経った後に、出頭日についての連絡が来ることが多いです。
もっとも、理論上は、判決言渡日に収監することも可能であると考えられており、一部の高等裁判所では判決言渡日に被告人が出頭したら収監されてしまったという情報もあります。
保釈請求が却下された場合の不服申立
保釈はお金を積めば釈放されるというものではありません。事案によって、金額にかかわらず認められないケースも多くあります。
保釈請求が却下された場合、不服申立をすることができます。
地方裁判所への準抗告、第1回公判後は高等裁判所への抗告という手続です。
保釈が却下された場合、被告人のところには却下されたという連絡だけが行きます。これに対して、準抗告などが却下された場合、却下の理由も届くので、どういう原因によるものなのか判明し、再度の保釈申請に役立てることが可能です。