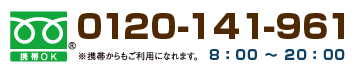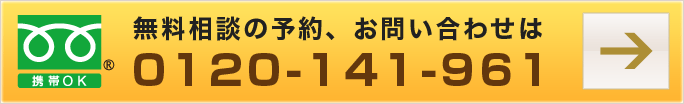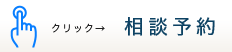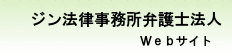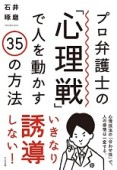逮捕後の弁護人
よくある質問(FAQ)
逮捕後の弁護人の活動は?
逮捕段階で刑事弁護の依頼があった場合、まずは被疑者のもとに接見に行きます。
逮捕直後の被疑者は動揺してしまっていることが多いです。
後々に不利な言動をしないよう、弁護人としては、被疑者の防御権を保障するため、早い段階で警察等に行き、被疑者と接見することが有効です。
事案にもよりますが、逮捕段階の目標としては、早期の身柄解放にあることも多いです。
逮捕後、まもなく勾留請求がされることが多く、勾留をさせたくない、早期に身柄解放を求める場合には、勾留請求に対する有効な反論ができるよう、有利な事情を集め提出できるよう準備が必要です。
勾留の理由の中でも、罪証隠滅を疑うに足りる相当な理由や、逃亡すると疑うに足りる相当な理由、その他、勾留の必要性がないこと、身柄解放の必要性について証拠化しておくのが有効です。
勾留請求前に、検察官に対し、勾留しないよう求める意見書や資料(示談書、誓約書、身元引受書等)を提出したり、面談交渉をすることもあります。
最近は、勾留を認める確率は以前より下がっているものの、裁判官によっては、自動的に勾留を認めているかのように感じることも多いです。
逮捕段階で弁護士への相談が入らないような場合には、各地域の弁護士会が対応している当番弁護士制度を使うもことも考えれます。
勾留請求後の弁護人の活動は?
検察官による勾留請求後、裁判官による勾留決定前に、裁判官と直接面会したり、勾留請求を却下するよう求める意見書等を提出します。
勾留要件に関する主張となるので、上記のように、誓約書や身元引受書も提出します。
裁判官による勾留決定前には、被疑者に対する勾留質問がされます。
勾留質問は勾留請求の当日にされることもあれば、翌日になることもあります。
以前は、勾留請求が却下されることは1%もなかったのですが、最近では、数%の割合で却下されることが出てきおり、事案によっては、弁護人を依頼したうえで早い活動をしてもらうだけの価値があるといえます。
勾留決定後の弁護人の活動は?
勾留決定後は、裁判所が認めた勾留事実を確認する必要があります。
通常は、裁判所に対して勾留状謄本の交付申請をおこなうことで、正確な被疑事実を確認できます。
一応、そこでは、勾留理由も確認できます。
ただ、ほとんどの場合、定型的な記載となります。
裁判官の勾留決定について争う場合には、勾留決定に対する準抗告をすることになります。
こちらも、近年、統計上は、認容率が上昇してきています。
身柄解放の必要性が高い場合には、積極的に対応します。
準抗告が棄却された場合には、特別抗告の申立が可能です。
ただし、申立期間は5日間とされます。
勾留理由の開示とは?
勾留の決定自体を争う準抗告以外に、勾留段階でおこなうことがある手続きとして、勾留理由開示請求があります。
これは、身柄の解放を求める活動ではないですが、被疑者が警察から移動し、裁判所の法廷で手続きが行われます。
公開法廷で行われますので、傍聴も可能です。
接見禁止がついている場合などには、事実上、被疑者と家族がお互いの顔を見ることができる機会にもなります。
勾留理由開示は、その名のとおり、裁判所に対して、勾留の理由を開示するよう求める手続きです。
この開示理由を確認したうえで、準抗告に利用したり、勾留の理由がなくなった場合に勾留取消請求に使ったりします。
勾留延長は?
勾留延長については、当初予定された期間から延長することができます。
検察官の求めにより、ほぼ自動的に延長されてしまう地域もあります。
勾留延長をさせないように、検察官に対して早い段階での捜査を促したり、不起訴意見害を提出することもあります。
勾留延長がされた場合、その延長自体に不服申立も可能です。
初回の接見場所は?
被疑者との面会のことを接見と呼びます。
通常、身柄拘束の初期段階では、被疑者は警察の留置場にいるため、警察の接見室で席巻することが多いです。
最近は、警察で複数の接見室を準備しているところが多いですが、一つしかなかったり、複数あっても一室でしか接見を認めないような警察では、接見が順番待ちになってしまうこともあります。
共犯事件では、事件を担当している警察署で主犯を勾留し、共犯者は別の警察署となることが多いです。
この場合、取扱い警察署と留置場所の警察署が異なっているため、接見しにくいタイミングもあります。
また、勾留手続き等で、被疑者の身柄が裁判所や、検察庁にある場合、裁判所によっては、裁判所等の接見室で接見できる場合もあります。
なお、弁護士が最初に接見する際には、家族等から選任されている場合を除いて、まだ弁護人として選任されていないので、弁護人となろうとする者という立場で接見します。当番弁護士の場合も同様です。
被疑者や被告人本人以外で、弁護人を選任できるのは、被疑者又は被告人の法定代理人・保佐人・配偶者・直系の親族及び兄弟姉妹と限られています。
通常は、委任契約は家族とした場合でも、被疑者と接見のうえで、被疑者から直接、弁護人選任届をもらいます。
被疑者段階での刑事弁護相談をご希望の方は以下のボタンよりお申し込みください。