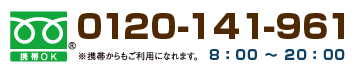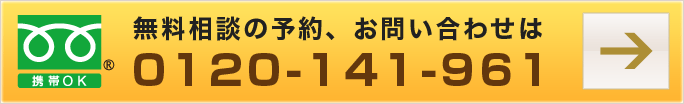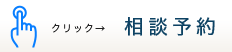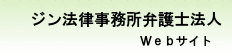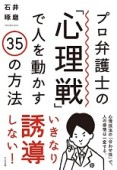よくある質問
よくある質問(FAQ)
タトゥー施術は医師法違反になる?
医師免許を持たないことで、医師法違反に問われる業務もあります。
タトゥー施術も医師法違反になるか争われました。
大阪高裁平成30年11月14日判決です。
事案の概要
タトゥー施術が医師法違反だとして起訴された事件です。
起訴された内容は次のようなものでした。
被告人は、医師でないのに、業として、平成26年7月6日頃から同27年3月8日頃までの間、大阪府吹田市内におけるタトゥーショップにおいて、4回にわたり、Aほか2名に対し、針を付けた施術用具を用いてAらの左上腕部等の皮膚に色素を注入する医行為を行い、もって医業をなしたとして、医師法17条、31条1項1号違反の罪で起訴されました。
医師法は、「医師でなければ、医業をなしてはならない」とし(17条)、これに違反した者は3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその併科に処されます(31条1項1号)。
判例上、「医業」とは反復継続の意思をもって医行為をなすことをいうとされていました(大判昭和8.7.8)
厚生労働省では「針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為」が医師法17条違反となりうると通知していました(2001年)。
大阪地方裁判所は、医師法17条にいう「医行為」とは「医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為」とし、弁護士人が主張していた医行為該当性には医療関連性等が必要であるとの主張を排斥、有罪としました。
被告人が控訴。
高等裁判所の判断
原判決を破棄、被告人を無罪としました。
まず、医師法の趣旨などを解説しています。
医師法は、「医療及び保健指導」という職分を医師に担わせ、医師が業務としてそのような職分を十分に果たすことにより、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保することを目的としているものです。
この目的を達成するため、医師法は、臨床上必要な医学及び公衆衛生に関して、医師として具有すべき知識及び技能について医師国家試験を行い、免許制度等を設けて、医師に高度の医学的知識及び技能を要求するとともに、医師以外の無資格者による医業を禁止しているとします。
医師の免許制度等及び医業独占は、いずれも、上記の目的に副うよう、国民に提供される医療及び保健指導の質を高度のものに維持することを目指しているとしています。
このような医師法の構造に照らすと、医師法17条が医師以外の者の医業を禁止し、医業独占を規定している根拠は、医業独占による公共的な医師の業務の保護を通じて、国民の生命・健康を保護するものである、言い換えれば、医師が行い得る医療及び保健指導に属する行為を無資格者が行うことによって生ずる国民の生命・健康への危険に着目し、その発生を防止しようとするものである、と理解するのが、医師法の素直な解釈であると思われるとのことです。
そうすると、医師法17条は、生命・健康に対して一定程度以上の危険性のある行為について、高度な専門的知識・技能を有する者に委ねることを担保し、医療及び保健指導に伴う生命・健康に対する危険を防止することを目的としているとする所論の指摘は、正当としました。
したがって、医師は医療及び保健指導を掌るものである以上、保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為であっても、医療及び保健指導と関連性を有しない行為は、そもそも医師法による規制、処罰の対象の外に位置づけられるというべきであるとしました。
タトゥーと医師法の趣旨
このような医師法の解釈に基づき、本件行為は、そもそも医行為における医療関連性の要件を欠いているというべきであるとしました。
彫り師やタトゥー施術業は、医師とは全く独立して存在してきたし、現在においても存在しており、また、社会通念
に照らし、入れ墨(タトゥー)の施術が医師によって行われるものというのは、常識的にも考え難いことであるといわざるを得ないとしています。
たしかに、医師にやれと言われても困りますね。
仮に、医療関連性という要件を不要とし、保健衛生上の危険性要件のみで足りるという解釈をとれば、本件行為は医行為に該当し、タトゥー施術業に医師法17条を適用することになります。
これだと、憲法が保障する職業選択の自由との関係で疑義が生じるのであり、このことからしても、医療関連性を欠くためタトゥー施術の医行為性を肯定することはできないという前記解釈適用の妥当性が支えられているというべきであ
るとしました。
タトゥーの彫り師にとっての職業選択の自由を重視した内容です。
タトゥー施術の危険性のフォローは?
タトゥー施術行為が起訴されたのは、その危険性からです。
そこで医師法の規制をしたほうが良いという考えで起訴されているわけです。
しかし、判決では、危険性のフォローについては別の方法でもできるとしています。
我が国でも、彫り師に対して一定の教育・研修を行い、場合によっては届出制や登録制等、医師免許よりは簡易な資格制度等を設けるとか、タトウー施術業における設備、器具等の衛生管理や被施術者に対する施術前後の説明を含む手順等に関する基準ないし指針を策定することなどにより、保健衛生上の危害の発生を防止することは可能であると思われるとしました。
タトゥー施術業が、医師が行うのでなければ保健衛生上の危害が生ずるおそれを伴うものであることを理由に、これを医師法17条の規制対象とする、すなわち、医師免許という厳格な資格制限による医師法の規制を及ぼすことは、他
により緩やかな制限が可能であることからすれば、規制の範囲が必要な限度を超えているものといわざるを得ないとしています。
このような内容で、原判決の結論は、憲法上の疑義が生じるといわざるを得ないとして破棄しました。
類似行為の判例
過去、医師法違反が争われた裁判例としては、アートメイクや植毛、レーザー脱毛がありますが、医行為に該当するとされていました。
今回、そのような行為と比較して、タトゥーについては否定という結論が出されたものです。
医師法違反等の刑事弁護相談をご希望の方は以下のボタンよりお申し込みください。