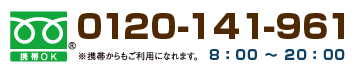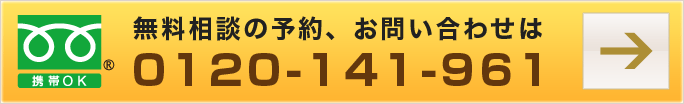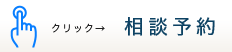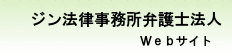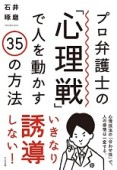よくある質問
よくある質問(FAQ)
児童福祉法の審判前の指導、勧告とは?
児童福祉法に基づき、一時保護中の児童について、里親等への委託又は児童養護施設への入所を承認するよう申し立てられた事案で、審判前の指導措置の勧告、申立てを却下に伴い、同条7項に基づく同内容の勧告がされた裁判例があります。
このような指導・勧告により親子関係が維持できるものと期待されていますので、紹介します。
福岡家庭裁判所令和元年8月6日の審判です。
事案の概要
申立人は、児童相談所長。
児童福祉法28条1項に基づき、 児童を里親等への委託又は児童養護施設への入所等の措置を承認する旨の審判を求めました。
児童については、両親が離婚。実母が親権者。
実母は、離婚した夫からDVを受けていました。また、幼少期には、父親から暴行を受けてもいました。両親は離婚。母親に引き取られたが、母親から自分を否定するようなことを言われて育っていました。
実母は、児童に対し、甘え行動を被害的に捉えて叩く、蹴るなどの暴行、「黙れ、触るな。」「4階から1階まで飛び降りろ。」「玄関で布団なしで寝ろ。」「お前が死ね。」などの暴言を浴びせていました。病院で傷口の縫合等の処置を必要とするまでの怪我を負ったこともありました。
児童も、同じよう「死ね。死ね。」などと暴言を吐く問題行動を起こしていました。
そして、児童が一時保護。
その後、母子は母子生活支援施設へ。施設の指導を受けていたものの、実母から児童に対し、怒鳴ったり叩いたりする言動が続き、児童は再度一時保護。
その後、本件申立てという経緯です。
裁判所の判断
結論としては申立を却下。
しかし、審判前の勧告や却下の審判時の勧告をするなどしてフォローがされた事案です。
裁判所は、実母に対する児童家庭支援センターへの定期的な通所、心理カウンセリングの受講、児童相談所の家庭訪問
や助言の受け入れ等を内容とする審判前の勧告をしました。
児童相談所に対し、期限を定めて、児童の保護者である実母に対し、指導措置を採るよう勧告がされているのです。
また、申立てを却下するに際し、家庭その他の環境の調整を行うため実母に対する指導措置を採るよう勧告がされています。
その内容は、児童相談所が指定する児童家庭支援センターに定期的に通所して、不適切な養育の内容を振り返り、児童の行動に対する適切な関係の取り方や母の精神的な問題について助言や援助を受けること、本件施設における心理カウンセリングを継続して受けること、児童相談所の家庭訪問や助言を受け入れ、連絡に応じ、生活状況等を報告することという内容でした。
児童や施設の対応
児童には暴言も見られ、周囲に対して、母の不適切な行為を訴える反面、母が悲しむから言えないなどと言うなど、相反する矛盾した言動や感情を示していました。
施設が母子関係調整及び母の学び直し等を各関係機関と協力して実施していくことが可能であるという内容の本件施設作成の意見書が提出されてもいました。
審判期日
実母は、期日において、児童との外出や外泊の際に、感情的にならないこと、目を離さないようににすること、施設の指導に従うこと、児童相談所の指導に従うことを誓約。
実母による監護でも、著しく児童の福祉を害するものとまでは評価し難いとされ、申立ては却下された一方で、児童相談所や施設と実母との関係性を維持し、不適切な養育が再発しないようにフォローするため、勧告を付したという内容です。
審判前の勧告とは
このような審判前の勧告は、保護者指導をすることで、良好な家庭環境にすることを目的とする制度です。
この制度は、認定できる事実関係から、28条1項の要件を満たすかどうか確定できないことが前提です。
確定できる場合には、申立を認容したり、却下したりすることになります。
裁判所は、児童福祉法28条4項により、母に対する指導措置の勧告を行ったところ、児童相談所の指導や本件施設の援助があり、これらの援助を母が肯定的に捉えているため、今は、大きな問題は露呈していないと認定しました。
そうすると、母の児童に対する監護が、改善され、著しく児童の福祉を害するものと評価し難いものとなっているとしました。
したがって、本件申立ては却下せざるを得ないとしています。
勧告をした理由
しかしながら、母と本件施設あるいは児童相談所との関係性に問題が発生すると不適切な養育が再発する可能性は今なお高いと認められるともしています。
すなわち、児童の愛着上の問題や母の成育歴に由来する精神的な問題の解決に関しては、正確な理解と適切な対応が必要であり、児童相談所等の専門機関による助言や援助を母が受け入れることがその前提となります。母は、その成育歴から「もともと人は信用できない」と思っているのであるから、その前提が崩れた場合、不適切な養育を自らの責任として自覚することが困難となり、従前の不適切な養育に戻る可能性は十分あり得ると危惧。
特に、母は、仕事上の悩みを抱えているところ、その解決方法について、 自身と児童相談所や本件施設の見解が異なった場合などに、援助を受け入れなくなるという可能性は否定できないとしました。
また、児童が父の存在を気にし始めており、同人から母は暴力を受けていたため、父を気にする児童とのかかわりの中で母の精神状態が不安定になることも否定できないとしています。
そうすると、指導勧告に基づく母に対する指導の効果は、いまだ十分でないと。
児童福祉法28条7項により、家庭そのほかの環境の調整を行うため、母に対して、指導措置を採るべき旨の勧告を付すものとしています。
少年事件、虐待等の相談をご希望の方は以下のボタンよりお申し込みください。