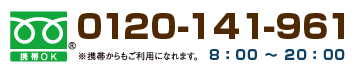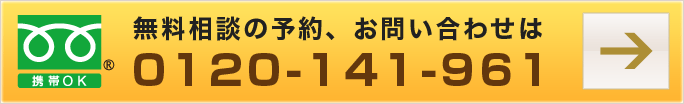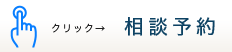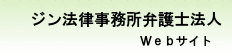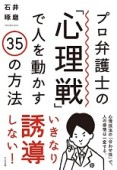よくある質問
よくある質問(FAQ)
13歳で少年院送致はあり得る?
13歳の少年事件でも、少年院送致という処分になることはありえます。
まだ、年齢が低いからと、本人、親ともが、軽く考えていると、重い処分を受けるということがありますので、注意が必要でしょう。
覚せい剤及び大麻を友人と共に密売人から譲り受け、これを単独で所持したという触法(覚せい剤取締法違反、大麻取締法違反)保護事件において、少年の薬物への依存性の深刻さ等を指摘し、少年を第1種少年院に送致した事例
東京家庭裁判所令和元年9月12日決定です。
事案の概要
当時13歳の少年。
覚せい剤及び大麻を友人と共に密売人から譲り受け、 これを単独で所持したという事件です。
認定された非行事実は、トイレ内において、氏名不詳者から、覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパン塩酸塩の結晶約0.870グラム及び大麻を含有する乾燥植物細片約4.829グラムを代金11万円で譲り受けたこと、この所持でした。
家庭裁判所の判断
少年を第1種少年院に送致するというものでした。
本件に至る経緯として、少年は、小学校5年生頃に母方祖母から将来のためにと両親に内緒で500万円ほどの現金を受け取って高級ブランド店に出入りするなどし、そこで声を掛けられた年長不良者らと一緒に遊ぶようになって、上記現金を上記年長不良者らに分散して預けるなどしていた点に触れられています。
その頃、少年は、不良年長者らに誘われて大麻を使用し、以後、3か月に1回程度の割合で使用を繰り返すようになり、中学入学前後頃にはLSDやコカインも使用するようになって薬物の使用頻度も増えていったという経緯です。
また、少年は、不良年長者らとクラブに頻繁に通うようになり、そこには様々な薬物が用意されており、それを自由に使用したりしていたほか、高級ホテルを借りて窓に目張りをした上で薬物を使用したりもしていたと指摘されています。
そうした中で、少年は、同級生らに薬物を勧めたところ、本件非行事実第1の共犯者がこれに興味を示し、大麻やコカインを一緒に使用するようになったと認定。
また、少年は、同級生らを誘って遊びに出掛けたり、ゲームセンターに行ったりすることを繰り返し、その際の多額の費用はすべて手持ちの現金や自宅から持ち出した現金で賄っていたと指摘。
そして、少年は、中学入学後、薬物を自ら購入するようになり、使用頻度もますます増え、平成31年・・・月頃には警察官の職務質問を受け、手荷物検査や身体検査を受けたものの、薬物を下着の中に隠していたことから発覚を免れたという状態。
この頃、少年は、薬物使用の影響で、目が真っ赤に充血したり、黒目が上を向いてまっすぐ歩けないことがあったり、同年・・・月末頃には在籍学校で少年が巻紙を落としたため、教師から薬物使用を疑われたが、少年は、証拠がないので違うと言い張って、その場を逃れたことがあったと指摘。
令和元年・・・月頃、少年は、手持ちの現金が乏しくなり、また、年長不良者らに警察の捜査が及びそうであったことから、薬物の使用を一時控えることとしたものの、その間も少年は、薬物使用と同様の効果を得ようとし、共犯者を誘って薬局で販売している咳止め薬を大量に摂取することを繰り返していたとのことです。
そうしたところ、現金を預けていた年長不良者から30万円くらいが戻ってきたことから、同月×日、少年は、共犯者を誘って薬物密売人の連絡先を探し出したが、薬物を購入することはできませんでした。そこで、少年は、共犯者に頼んで薬物を購入してもらうことにして、共犯者が薬物の譲受け。
そして、翌日、少年は、通学先の中学校で薬物を受け取り、トイレの個室内で、始業前と授業の合間の3回にわたり、あらかじめ用意していた学校給食用のスプーンとライターで覚せい剤をあぶって吸引したが、それほど効果を感じなかったことから覚せい剤のかけらを口に含んで授業を受け、さらには、授業中に譲り受けた大麻を机の下ではさみを使って切り刻んでいたところを教師に見つかり、薬物所持が発覚。
依存性が深刻
裁判所は、少年が述べるところによると、少年がこれまでに使用した薬物は、大麻、覚せい剤、LSD、MDMA、ヘロイン、モルヒネ及びコカインというのであり、覚せい剤の使用は本件時が2回目であるものの、その余は相当多数回に及び、使用頻度、使用量も増加していることなどに照らし、少年は、少なくとも薬物に対する精神的依存症状を示すに至っており、薬物への依存性は深刻であると認定しています。
鑑別結果等
鑑別結果等によれば、少年は、年齢相応以上の能力を有しているものの、注意欠如多動症(不注意性優位状態)疑い及び自閉スペクトラム症疑いと診断される発達上の特質が認められると指摘。
そのため、その場の雰囲気を読んだり、他者の気持ちや思いをくんだりすることが苦手であり、また、活動性が高い一方で抑制力が乏しく、その場の思い付きや気分で即行的に行動しがちであることから、自己本位で場にそぐわない行動を取ることが多く、周囲の不評を買いやすいとしています。
しかし、上記の発達上の特質から自分の問題には目が向きにくく、周囲が自分のことを分かってくれないなどと受け止めて、一方的に寂しさや不信感を募らせ、周囲の指導をその場限りのものとして受け流しがちであるとしています。また、少年は、毎日を面白おかしく過ごしたり、派手さや華やかさを求めたりするなど強い刺激を好み、派手に振る舞いやすく、他者と対等に付き合うことができにくいことから、構ってくれる相手には安易に付いて行ったり、相手に得があれば関係を維持できるだろうという発想から物や金で関心を引いたりすることで寂しさを埋め合わせようとすることが多いとしています。
非行の背景
薬物自体の依存性の深刻さのほか、少年が、多額の金銭を使い、また、薬物を使用してまでも友人らと楽しく過ごしたいとして、年長不良者らと一緒に、あるいは自ら単独で、薬物を使用し、更に同級生らにも薬物を勧めていることからすると、少年にとって薬物は、対人関係の形成、維持の手段として定着しているということができると指摘しています。
さらに、少年は、不快な状況に対してどう対処してよいかわからず、不快感情を適切に処理することもできにくいなかで、金銭の浪費や違法薬物といった強い刺激で不快さを紛らわすといった逃避的な手段を取りやすく、これまでの少年と薬物との関わりや、本件においては学校内で、しかも授業中にもかかわらず薬物を使用するなどしていることからすると、社会のルールよりも興味関心や欲求を優先させるという少年の行動傾向は極めて顕著であると評価しています。
本件非行の背景には、このような少年の資質、行動傾向上の問題が深く関わっているが、少年自身、自分は薬物に依存していない、薬物をやめることはできるなどと安易に述べるなど自己の問題に目を向けることができずにいることからすると、再非行危険性は相当高く、少年の問題の改善は相当困難としています。
少年の環境面
少年を取り巻く環境についてみると、両親は、少年に対する関心と指導の意欲を有しているが、少年の金銭の持ち出しを知っても自宅に多額の現金を置いたままにするなど、金銭管理が十分とはいえず、結果としてこれまで少年の問題行動を助長させてきたということができると指摘。
父親は、少年に寄り添ってきてはいるが、教育熱心のあまり、少年の心情を理解しようとする姿勢に欠け、生活に関しても賞罰を伴った規制を行ってきており、少年は、父親に親和しつつも家庭内で窮屈さを感じており、その反動が少年の年長不良者との交友や目が届かないところで羽目を外したり、奔放な振る舞いをしたりという行動の一因となっていると評価。また、母親は、少年の発達上の特質をなかなか受け入れることができず、ひたすら少年を信頼するという姿勢を持ち続けてきていると認定。
そして、両親、特に父親は、本件非行内容及び少年のこれまでの薬物との関わりを知っても、医療機関の指導を受けることで少年と薬物との関わりを断つことができるなどと楽観的な見通しを述べるにとどまり、少年の薬物への依存性の深刻さについての理解が不十分であるというほかないと厳しく指摘。
したがって、少年の改善更生に向けた両親の指導監督に多くを期待することは困難というべきであると結論づけています。
少年事件の中では、比較的、教育に積極的な親だと感じられましたが、その方向性について厳しい評価がされています。
裁判所の結論
このような事情から、本件事案の重大性や少年の薬物への依存性の深刻さ、少年の資質及び行動傾向上の問題の根深さとその改善の困難さ、少年の保護環境などに照らすと、少年が現在13歳であり、少年にはこれまで保護処分歴がないことや、本件を受けての保護者の少年の指導監護に向けた意欲の高まりなどを考慮しても、少年に対しては、系統的で強固な枠組みの下、時間をかけて少年の資質面の問題に即した地道な指導を行うことにより、薬物との断絶を果たすと共に、健全な対人関係を形成する能力や社会性、規範意識を身に付けさせることが必要不可欠であり、少年を少年院に収容することが特に必要と認められるとしました。
14歳未満での少年院送致
少年法では、年少少年については、 児童福祉機関の措置に委ね、同機関が相当と判断した場合に家庭裁判所の審判に付することができるとしています。
過去の少年院法では、初等少年院及び医療少年院の収容可能年齢は14歳以上とされていました。
その後、少年院法が改正。
少年院に収容することができる者の年齢が「おおむね12歳以上」に引き下げられました。
ただし、決定の時に14歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認める場合に限りとされています。
あくまで、例外的な決定といえます。
今回の少年の非行は、学校での使用などもあり、周囲への影響は大きかったといえます。そのような点を重視し、少年の特性などから処分を決めたものと思われます。
教育熱心な親という認定もされていることから、監護結果や調査官による調査結果から、うまく更生の方向性に導けなかったものかとも感じてしまいます。
刑事弁護をご希望の方は以下のボタンよりお申し込みください。